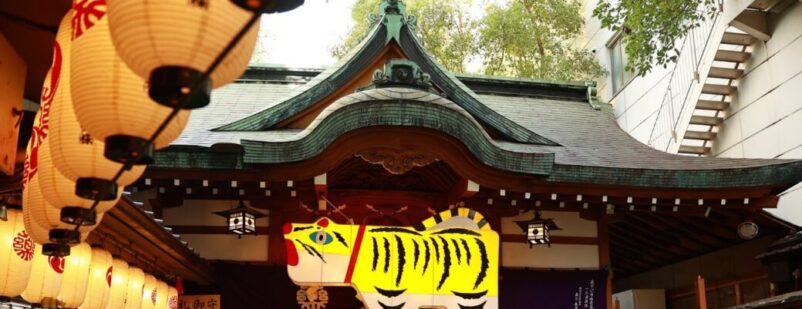1.作法に必要な論理と想像力 「型」は理論 茶道では「袱紗捌き」があります。 何何度も袱紗を広げて、また折りたたみます。 お茶の道具を拭くために必要な行為ですが、面倒に思えます。 短期間ですが茶道を習ったことがあります。 その時に、袱紗捌きの本当の意味が理解できました。袱紗の清潔な面でお茶の道具を拭き清める。そのために、広げ折り返すのだということがわかったのです。 袱紗に余計な皺をつけず、必要以上に袱紗を広げないで、常に清潔な面をお道具に当て清めるための無駄のない動きです。それが、袱紗捌きの「型」として継承されてきています。 作法にも様々な「型」があります。 夜露キビ事や悲しみ事の儀式から、歩 …
この続きは、ロンダンを定期購読頂くことで閲覧が可能です。
価格:月額1100円(税込)
ログインして閲覧する 会員登録して購入する